※この記事は生成AIが書きました。
【目次】
- はじめに
- コールドストーンとは――ブランドと成功の原点
- 臨場感マーケティングとは何か
- コールドストーンとアイス市場の動向
- メリット・デメリットで読むコールドストーンの戦略
- 店舗・人件費・物価高の三重苦
- 日本撤退の背景とファン心理
- ターゲット戦略の変遷
- コールドストーンの事例から分かるマーケティング課題
- 今後のアイスビジネスのヒント
- まとめ
1. はじめに
「出来たてアイスクリーム」の圧倒的な臨場感とエンターテインメント性。コールドストーンは、1998年に日本参入を果たし、その感動体験で多くのファンを魅了しました。しかし2022年3月には日本の直営店舗が全て閉店し、話題に。その背景には、単なる「アイス」の提供を超えたマーケティング戦略と、現代日本が抱える飲食業界全体の課題が浮かび上がります。本記事では、キーワード「アイス」「臨場感」「店舗」「撤退」「ファン」「人件費」「物価高」「ターゲット」「メリット・デメリット」「事例」「課題」に着目し、コールドストーンを深掘りします。
2. コールドストーンとは――ブランドと成功の原点
コールドストーン・クリーマリーは、アメリカ・アリゾナ州で1988年に誕生。「-9℃に冷やした石(コールドストーン)」上でアイスクリームと様々なミックスイン(トッピング)を混ぜて提供する新感覚スタイルをそのまま名前とビジネスに取り入れました。
日本上陸当初は、「目の前で歌いながら作ってくれる」という、非日常の店舗体験がSNS映えするスポットとして注目され、話題となりました。この臨場感溢れる演出が熱狂的ファン層を生み出したのです。
3. 臨場感マーケティングとは何か
コールドストーン型の「臨場感マーケティング」とは、五感全てに訴えかけるサービス体験を作り、単なる商品の枠を超えてブランド価値を構築する手法です。
臨場感の三大要素(コールドストーン事例)
| 要素 | 具体的な仕組み |
|---|---|
| 視覚・聴覚 | スタッフの歌やパフォーマンス、店内ディスプレイ |
| 味覚・嗅覚 | 出来立てアイスと甘い香り |
| 触覚 | 目の前でミキシングする温度・動きの体感 |
これにより、「またこの体験を味わいたい!」という再来店動機を醸成することができます。
4. コールドストーンとアイス市場の動向
日本は世界的にもアイスクリーム消費大国ですが、その中心は「家庭用」「コンビニ用」のパッケージアイス。コールドストーンはこの中で「高級・エンタメ系店舗アイス」という新しい価値を提案しました。以下のような市場セグメントで差別化を図ったのです。
アイス市場のセグメントとコールドストーンの位置付け
| セグメント | 主な商品/特徴 | メイン顧客 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| コンビニ・家庭用 | 市販アイス | 幅広い年齢層 | 低〜中 |
| パーラー系 | サーティワン等 | 若年層・家族 | 中 |
| コールドストーン | “臨場感”×プレミアム | 若年・カップル | 高 |
体験提供型の高付加価値戦略でしたが、「食べる娯楽」のトレンド変化、店舗運営コストの高騰といった課題も直面します。
5. メリット・デメリットで読むコールドストーンの戦略
コールドストーン型戦略の強みと弱み
| メリット(強み) | デメリット(弱み) |
|---|---|
| 他にはない臨場感・エンタメ性 | 複雑なオペレーションで人件費が高くなる |
| SNS拡散・話題性で集客力が高い | 慣れや飽きのリスクが生まれやすい |
| プレミアム価格帯を受容しやすい顧客層への訴求 | 価格帯が高く、リピートを狙いづらい |
一度は熱狂的なファンを獲得できますが、継続的な体験提供やコスト管理の難しさが浮き彫りとなりました。
6. 店舗・人件費・物価高の三重苦
コールドストーンの臨場感演出を維持するためには、広いカウンター・複数スタッフ(しかもパフォーマンス-trained)が必須。近年の人件費高騰や物価高も追い打ちとなりました。
店舗運営コストの例(業界平均値比較でイメージ)
| コスト項目 | 一般的な飲食チェーン | コールドストーン型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 標準 | 高 | オーダー対応・ミキシング・パフォーマンス等複雑 |
| 設備費 | 標準 | 高 | 専用カウンター・冷却ストーン等が必要 |
| 材料費 | 標準〜やや高い | やや高い | 多種類トッピング・アイスの品質キープ |
これらの構造的コストが、日本の「飲食店短命化」風潮もあり、長期運営をさらに困難にしました。
7. 日本撤退の背景とファン心理
コールドストーンの日本直営店撤退(2022年)は、地道な業績不振が要因であり、特にコロナ禍による人流減少、テナント賃料・人件費高騰が直撃したと考えられます。
ファン心理の変容
熱心なコールドストーンファンの多くは「体験価値」への忠誠心を備えていました。しかし、習慣化や新鮮さの消失、生活防衛意識の高まりによる「贅沢品離れ」も見て取れました。
| ファン層の移り変わり | 主な購買動機 |
|---|---|
| 参入初期:熱狂層 | 非日常体験、SNS映え、デートなど |
| 定着期:一般層 | “たまにのご褒美” |
| 退潮期:コア層のみ | 想い出の味、エモーショナルバリュー |
8. ターゲット戦略の変遷
コールドストーンのメインのターゲットは、「若年層」「カップル」「ファミリー層」など、“体験消費”を楽しむ層でした。しかし、時代が進むにつれ、以下のような課題が生じます。
ターゲット別メリット・デメリット
| 顧客層 | メリット | 課題・リスク |
|---|---|---|
| 若年層 | SNS等で情報拡散、話題化しやすい | 飽きやすい、流行が変わるスピード早い |
| カップル/友人 | 記念日・デート需要を獲得 | 価格に対する抵抗感が年齢と共に増す |
| ファミリー | 子連れで楽しめる非日常性 | ファストフードや他スイーツ店との競争激化 |
日常的に通う「習慣型消費」にシフトできなかった点も撤退要因の一つでした。
9. コールドストーンの事例から分かるマーケティング課題
事例1:臨場感の標準化困難
コールドストーンの店舗拡大時、多店舗展開で品質と臨場感パフォーマンスの「均一化」が困難でした。特定店舗だけスタッフの歌が下手だったり、サービスが機械的だったりという口コミも。この“人依存”体験は巨大化しにくい課題を持っています。
事例2:物価高・人件費高との戦い
2020年代に入り、商業施設の賃料上昇や人件費高騰、原材料の調達コスト増大が激化。アイス原材料の“高付加価値化”競争が進む一方、コールドストーンの「高価格訴求」はボリュームゾーンの顧客には刺さりにくくなりました。
事例3:撤退後の商品展開
撤退後、コンビニ・量販店向けのパッケージアイスや期間限定コラボなどでブランドは継続。しかし、臨場感や店舗での熱狂体験は再現できず、「あの体験をもう一度」というファン層の再獲得には至っていません。
| マーケティング課題 | 具体例 |
|---|---|
| 体験の標準化難易度 | サービス品質にバラつき、リピーター化障壁 |
| コスト増加への弱さ | 人件費・原材料費・賃料いずれも上がる |
| 商品価値の維持困難 | 単なるアイスでは他社と差別化しにくい |
10. 今後のアイスビジネスのヒント
コールドストーン撤退のような事例から、アイスビジネス(特に体験型ビジネス)が次世代で求められるものには以下のポイントが挙げられます。
これからの戦略ヒント
| 戦略 | 具体例 |
|---|---|
| 省人化・テクノロジー活用 | AIレジ、自動ミキシング機などで人件費削減 |
| 体験の新しい価値提案 | ARやデジタル連携のイベント展開 |
| 商品ラインナップの見直し | イートイン+テイクアウト・デリバリー拡充 |
| サブスクリプション導入 | 常連リピーター向けの会員特典・限定体験 |
プレミアム体験の一方で、日常の“自分ご褒美”領域もマーケット成長が見込まれています。
11. まとめ
「アイス」を通じて非日常の「臨場感」体験を生み出すコールドストーンのマーケティングは、日本の飲食業にさまざまな示唆を残しました。時代の変化と共に、店舗オペレーションや人件費・物価高といった課題が経営を圧迫し、店舗撤退へと至りましたが、「ファン心理」や「体験の価値」は今なお大きな示唆を持っています。
今後は省力化と高体験価値の両立、新たなターゲットの発見、デジタルや自動化との連動が、アイスビジネスの勝ち筋となるでしょう。あなたがアイス屋さんを始めるなら、コールドストーンの成功と失敗事例をぜひ研究してみてください。















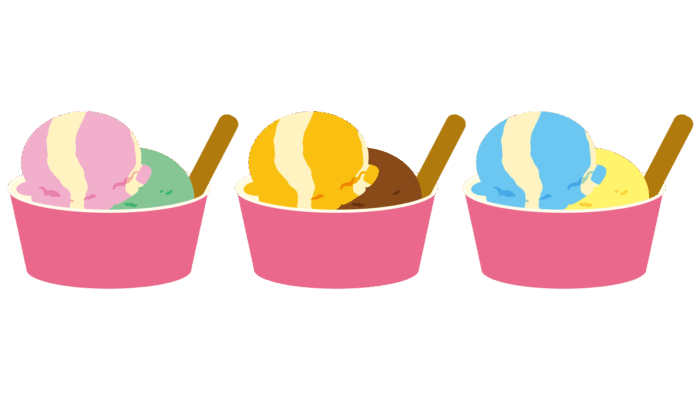

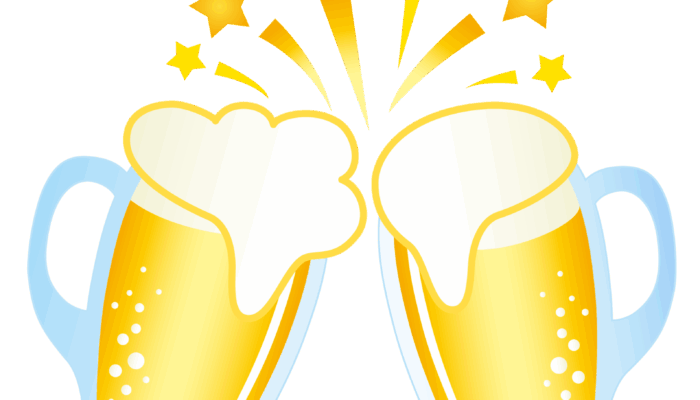
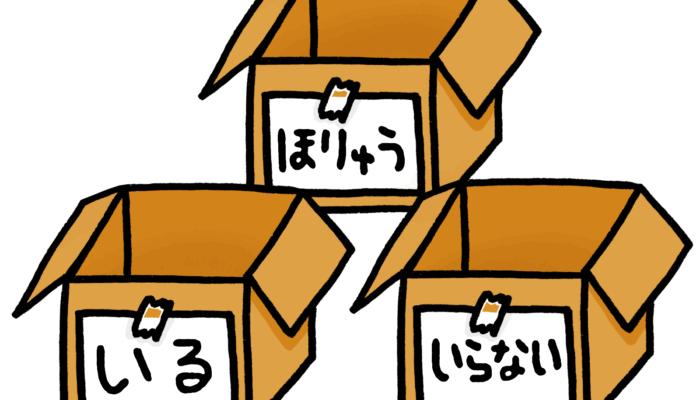
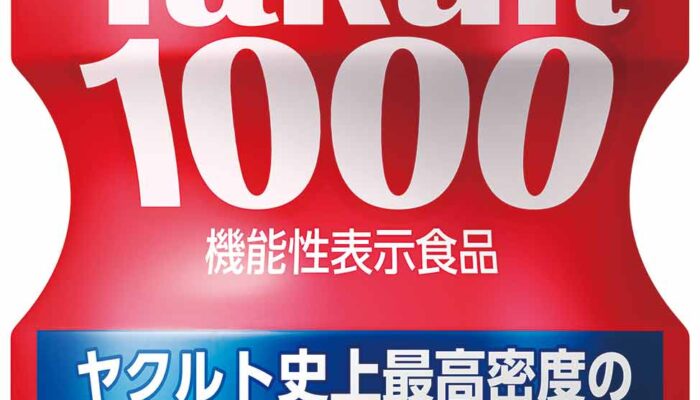



コメント