― EC・通販ブランドが“利益”と“ブランド力”を同時に上げる設計図 ―
目次
- ブラックフライデーとは?世界と日本での位置づけ
- なぜ今、EC・通販市場にとってブラックフライデーが“外せない日”なのか
- 「安くするだけ」はもう古い? 新メニュー・高価格帯を仕込む発想
- ブランディングとUSPから逆算するブラックフライデー戦略
- 施策別「メリットとデメリット」を整理する(比較表)
- ターゲット別コミュニケーション設計(比較表)
- 成功要因と、ブラックフライデーでよく起こる“失敗パターン”
- 中小EC・個人ブランドが今年からできる実践ステップ
- まとめ:一年でいちばん「学べる」セールにする
1. ブラックフライデーとは?世界と日本での位置づけ
アメリカ発「一年で最も忙しい買い物の日」
ブラックフライデーとは、アメリカの感謝祭(11月第4木曜日)の翌日に行われる、大規模なセールの日です。もともとは、感謝祭翌日に人と車が街にあふれ、大混雑になる様子を警察が「ブラックフライデー」と呼んだことが始まりとされ、その後「この日を境に小売店の帳簿が赤字(red)から黒字(black)に転じる日」というポジティブな意味合いで定着していきました。(ウィキペディア)
現在では、実店舗だけでなくECでも大規模セールが行われ、クリスマス商戦のスタートを告げるイベントとして、世界中に広がっています。(ウィキペディア)
日本におけるブラックフライデー
日本では感謝祭という文化はありませんが、大手量販店やショッピングモール、ECモールがブラックフライデーを独自に導入することで広まりました。特に、イオングループなどの小売と、Amazonや楽天市場といった大手ECモールがキャンペーンを展開し始めたことで、2010年代後半から一気に認知度が上がっています。(Bottleship Marketing)
日本のブラックフライデーには、アメリカと比べて次のような特徴があります。
- 期間が長い:ある一日だけではなく、11月中旬〜下旬にかけて数日〜数週間のセールを行うケースが多い(Stripe)
- EC・通販中心:深夜から並ぶ“突撃型”より、オンラインでじっくり比較して買うスタイルが主流(eSIM Japan)
- 「年末商戦のスタート」という意味合い:年末年始セールや福袋、初売りにつながる“最初の山”として位置づけられている(Stripe)
さらに、日本の消費者は「量より質」を重視し、ポイント還元や限定品、セット商品など“お得感+特別感”に価値を感じる傾向が強いと言われます。(Covue)
つまり、ブラックフライデー=とにかく安く売る日と捉えるのは、かなりもったいない。
日本のEC・通販市場では、もっと「戦略的な活用余地」が残されています。
2. なぜ今、EC・通販市場にとってブラックフライデーが“外せない日”なのか
年末まで続く「購買モードON」のスイッチ
ECや通販の立場から見ると、ブラックフライデーは、単なる売上の山ではなく、顧客の“購買モード”にスイッチを入れる起点です。
- このタイミングで、「今年はどういう買い方をしようか」と考え始める
- 各社のセールを比較しながら、候補ブランドのリストが頭の中にできあがる
- ポイント残高やクーポン、年末のボーナスの使い方を意識し始める
こうした行動変化は、日本の年末商戦全体の売上や、小売全体の11月の小売販売額にも表れているとされます。(Reuters)
つまり、ブラックフライデーは**「今年、どのEC・通販を“推しブランド”にするかを決める最初の接点」**になりやすいのです。
ECにとっての「実験場」としての価値
ブラックフライデーは、次のような意味で、EC・通販にとって最高の“実験場”でもあります。
- 新メニュー(新商品・新サービス)のテスト
限定フレーバー、コラボ商品、サブスクの特別プランなどを、短期間で露出・検証できる。 - クリエイティブ・コピーのA/Bテスト
LP、バナー、メール、SNS広告を同時多発的に回し、どの打ち手が刺さるかを学べる。 - ターゲットセグメントごとの反応差の可視化
新規顧客、リピーター、休眠顧客など、セグメント別にオファーを変えて反応を見ることで、翌年以降のCRMに活かせる。(BigCommerce)
「セールだから利益が削られる」のではなく、
**「学習コストを払って、来年以降のLTVを最大化する投資の場」**と捉える視点が、マーケターには必要です。
3. 「安くするだけ」はもう古い?
新メニュー・高価格帯を仕込む発想
ブラックフライデーというと「割引率何%オフ」というイメージが強いですが、
差別化を図りたいブランドほど、**“安さ勝負以外の軸”**を用意すべきです。
ここでキーワードになるのが、新メニューと高価格帯です。
3-1. 新メニューを出すなら「お試し」より「世界観」を見せる
ブラックフライデーで新メニュー(新商品・新プラン)を投入する場合、
単なる“お試し用の廉価版”にしてしまうと、USPもブランディングも弱くなります。
むしろ、
- ブランドの世界観
- コアな価値観
- 将来出していくラインナップの方向性
を象徴するような商品を出す方が、EC・通販の「ファン作り」には有効です。
例:
- コーヒーEC:
通年商品とは別に、産地や焙煎哲学を前面に出した「ストーリー性のある限定セット」を新メニューとして出す。 - D2Cコスメ:
成分だけでなく、使用シーンやライフスタイルの提案をパッケージや同梱冊子で語る特別企画品を出す。
ブラックフライデーは、**「うちのブランドは、こういう価値観で勝負します」**と宣言するタイミングとしても使えるのです。
3-2. なぜあえて高価格帯を仕掛けるのか
セールだからといって、すべてを低価格に寄せる必要はありません。
むしろ、高価格帯の商品を打ち出せるブランドほど、市場でのポジションが安定しやすいと言えます。
- 「普段は手が届かないが、この機会なら」と思わせる高価格帯ライン
- 体験やストーリーをセットにしたプレミアムパッケージ
- 長期保証やコミュニティ参加権など、金額以上の価値を見せる設計
ブラックフライデーだからこそ、“高価格帯のUSP”を分かりやすく提示するチャンスになります。(firework.com)
4. ブランディングとUSPから逆算するブラックフライデー戦略
値引き率からではなく、ブランドの方向性とUSPから逆算するのが、ブラックフライデー設計の基本です。
4-1. まず「どんなブランドとして記憶されたいか」を決める
- 「圧倒的にコスパが良いEC」として記憶されたいのか
- 「高価格帯でも納得感のあるプレミアムブランド」として認識されたいのか
- 「新メニューやコラボが楽しみな、遊び心ある通販ブランド」にしたいのか
この軸が固まっていない状態で、
「他社が◯%オフだから、うちも…」と値引きだけ真似すると、
ブランドのブレや、顧客の混乱を招きます。
4-2. USPを“オファー”に翻訳する
USP(Unique Selling Proposition)は、単なるフレーズではなく、
オファー(具体的な提案)に落とし込まれたときに初めて、売上に効きます。
- 「プロが選んだ厳選◯点」 → ブラックフライデー限定の“プロセレクトセット”
- 「長期的なサポート」 → セール期間中の申込だけ、サポート期間を延長
- 「コミュニティ性」 → 購入者限定のオンラインイベントや限定コンテンツへの招待
USPを「何を・誰に・どう届けるか」という形で設計し直すと、
ブラックフライデーのオファーも、ブランディングと一貫性を持たせやすくなります。(markopolo.ai)
5. 施策別「メリットとデメリット」を整理する(比較表)
ブラックフライデーの施策は、ざっくり次のようなタイプに分けられます。
それぞれのメリットとデメリットを整理しておきましょう。
表1:ブラックフライデー施策タイプ別「メリットとデメリット」
| 施策タイプ | 概要 | 主なメリット(EC・通販側) | 主なデメリット・リスク |
|---|---|---|---|
| 大幅値引き型 | 定番商品の価格を一気に下げる | トラフィックが増えやすい/在庫処分に向く | 粗利の圧迫・安売りイメージ/リピーターの単価下落 |
| セット売り・バンドル型 | 複数商品をまとめてお得なセットにする | 客単価アップ/在庫の組み合わせ調整がしやすい | セット内容が魅力的でないと、逆に複雑に見える |
| 高価格帯プレミアム型 | 通常より高い価格帯の限定商品や体験型商品を出す | ブランドの格を上げやすい/コアファンのLTV向上 | 売上数量が読みづらい/説明不足だと「高いだけ」に見える |
| サブスク・会員制サービス訴求型 | 月額・年額の定額制サービスに特典を付けて販促する | 継続課金による安定収入/LTV最大化につながる | 解約率とのバランス設計が必要/サポート負荷が増える |
| 新メニュー・新ブランドお披露目型 | 新商品・新ラインをセールと同時にローンチする | 話題化しやすい/既存顧客に新カテゴリーへのクロスセルがしやすい | 準備負荷が高い/短期で評価されやすく中長期検証が難しい |
このように、どの施策にもメリットとデメリットがあります。
重要なのは、自社のターゲットと市場ポジションに合った組み合わせを選ぶことです。
6. ターゲット別コミュニケーション設計(比較表)
ブラックフライデーは、「誰に」「何を期待して」来てもらうかを決めないと、
ただアクセスが増えるだけの“お祭り騒ぎ”で終わってしまいます。
表2:ターゲット別コミュニケーションの軸
| ターゲット | 主なニーズ・心理 | 刺さりやすいメッセージ例 | 有効なチャネル例 |
|---|---|---|---|
| 初めて訪れる新規顧客 | お得に試したい/失敗したくない | 「初回限定・人気セット」「口コミ高評価から厳選」 | SNS広告、インフルエンサー投稿、SEO |
| 既存のリピーター | いつも買っているブランドで、少し贅沢したい | 「会員限定」「いつもありがとうございます。特別セットをご用意」 | メール、LINE公式、アプリPUSH |
| 休眠顧客・しばらく購入がない顧客 | 以前の印象は良いが、他ブランドへ流れている | 「お久しぶりの方へ」「前回からアップデートしたポイントを紹介」 | メールリマインド、リターゲティング広告 |
| 高価格帯を受け入れる“コアファン” | ブランドを応援したい/限定感・特別感を求める | 「ブラックフライデーだけのプレミアム体験」「数量限定コレクション」 | 限定コミュニティ、DM、クローズドSNS |
| 比較検討に時間をかける慎重派ユーザー | 損をしたくない/長期的なコスパを重視 | 「長期保証」「サポート内容を詳細に」「他社との違いを丁寧に説明」 | 比較記事LP、レビューコンテンツ、FAQ |
ここで意識したいのは、
ターゲットの心理に合わせて、訴求する“メリット”を変えることです。
同じブラックフライデーでも、
- 新規には「失敗しない安心感」
- コアファンには「限定性とブランドへの共感」
といった形で、コミュニケーション内容を変えていく必要があります。
7. 成功要因と、ブラックフライデーでよく起こる“失敗パターン”
7-1. 成功しているEC・通販に共通する「成功要因」
ここ数年のブラックフライデーを観察すると、成功しているブランド・ECには、次のような共通点があります。(Next Level)
- ゴールが「売上」だけで終わっていない
- 新規会員登録数
- メルマガ・LINE登録数
- レビュー投稿数
- サブスク・定期購入への移行率
といった中長期の指標を、最初からKPIとして置いている。
- キャンペーン設計が「ストーリー」になっている
- ブラックフライデー → サイバーマンデー → クリスマス → 正月
までを一つのストーリーとして捉え、「続きが気になる」構成になっている。
- ブラックフライデー → サイバーマンデー → クリスマス → 正月
- ECサイトの体験に“ローカライズ”が効いている
- 日本人が重視するレビュー表示や、ポイント還元の見せ方が丁寧
- 配送・返品ポリシーが、年末の忙しい時期でも安心して使える設計になっている(Covue)
- データと顧客の声を、翌年のブラックフライデーにきちんと活かしている
- CVRやLTVだけでなく、問い合わせ内容やSNSのコメントも含めて振り返りを行う。
- 「今年の学び」を必ずドキュメント化している。
7-2. よくある失敗パターン
逆に、よくある失敗パターンは次のようなものです。
- 安くしすぎて“後戻りできない”価格認知を作ってしまう
→ 通常価格に戻した途端、売れなくなり、「常に何かしら割引しているブランド」というイメージがつく。 - 在庫とオペレーションを甘く見積もる
→ 人気商品が一瞬で売り切れ、広告だけ回り続けてしまう。
→ 倉庫やカスタマーサポートがパンクし、口コミでの評価が下がる。(ウィキペディア) - ターゲット不在の“なんでもセール”をしてしまう
→ ページもLPも「全部安いです!」だけで、結局何を買えばいいか分からない。
→ ブランドのUSPが見えず、比較サイトの一枠として埋もれてしまう。
ブラックフライデーは、売上のチャンスであると同時に、
ブランドの弱点も露骨に炙り出されるイベントだと言えます。
8. 中小EC・個人ブランドが今年からできる実践ステップ
「うちは小規模だから、ブラックフライデーなんて…」
そう感じるEC・通販も多いですが、むしろ小さなブランドほど、尖った戦略で差別化しやすいタイミングです。
ステップ1:今年は「たったひとつの目的」に絞る
- 新規顧客を増やしたいのか
- メール・LINEリストを増やしたいのか
- サブスク・定期購入に移行させたいのか
- 高価格帯商品のテストをしたいのか
目的が複数あると、メッセージも施策もブレてしまいます。
今年は一つに絞り、他は“ついでに取れたらラッキー”くらいに構えるのが現実的です。
ステップ2:ターゲットを“具体的な人物”レベルまで落とす
「20〜40代の男女」ではなく、
- どんな仕事・ライフスタイルか
- 何曜日・何時にECを見ることが多いか
- どんな比較サイトやSNSをよく使うか
- 年末の買い物で、何を重視しているか
といった粒度までターゲットを具体化します。
ブラックフライデーのような混雑した市場では、
抽象的なターゲット設定 = 誰にも刺さらないメッセージになりがちです。
ステップ3:新メニュー or 高価格帯のどちらかを「必ず」仕込む
たとえ小さい規模でも、
- 限定セット
- 特別な組み合わせ
- 通常は出さない高価格帯のフルラインセット
といった“ブラックフライデー専用のメニュー”を1つ以上用意しましょう。
これが、そのまま**自社ECのUSPの「実物見本」**になります。
ステップ4:メリットとデメリットを「正直に書く」
ブラックフライデーのLPや商品ページでは、
メリットだけでなく、あえてデメリットや向かない人も書くことが、
結果的にコンバージョンの質を高めます。
例:
- 「じっくり味わいながら楽しみたい方向け。
とにかく量を求める方には向きません。」 - 「定期的に使う習慣がある方向けのサブスクです。
一度だけ試したい方には“単品購入”をおすすめします。」
こうした“正直さ”は、日本の慎重なECユーザーの信頼を得やすいポイントでもあります。(Covue)
ステップ5:終わった直後に「来年のメモ」を残す
ブラックフライデーが終わった直後こそ、
- 何がうまくいったか
- どこに課題があったか
- どのターゲットがよく反応したか
をざっくりメモに残す絶好のタイミングです。
翌年になると、「細かい感覚値」はきれいさっぱり忘れてしまいがち。
たとえ一枚のメモでもいいので、**“来年の自分へのラブレター”**として残しておくと、
毎年ブラックフライデーの精度が上がっていきます。
9. まとめ:一年でいちばん「学べる」セールにする
ブラックフライデーは、
単なる「大セールの日」ではなく、
- EC・通販市場全体の空気が一気に“購買モード”になる日
- 自社のブランディングやUSPが、世の中にどう見えているかが試される日
- 新メニューや高価格帯ラインをテストできる、貴重な実験の場
だと言えます。
ポイントは、安売りの日として終わらせないこと。
- ターゲットを具体的に絞る
- ブランディングとUSPから逆算してオファーを作る
- 施策ごとのメリットとデメリットを理解したうえで選ぶ
- キャンペーン全体を「一年かけて育てる企画」の一部として設計する
こうした視点でブラックフライデーに向き合えば、
売上だけでなく、ブランドのファン・ECとしての信頼・来年への学びを同時に手に入れられます。
あなたのブランドにとって、
「ブラックフライデー=最も利益率が悪い日」ではなく、
「ブラックフライデー=一年でいちばん学びと成長が大きい日」
に変えていきましょう。
その第一歩として、
今年は「たったひとつの目的」と「ひとつの新メニュー/高価格帯ライン」を決めるところから、静かに始めてみてください。
この記事を書いたライター

ゆいマーケメディア編集部
今話題になっているテーマを、マーケティング視点で分かりやすく記事にして解説します!
















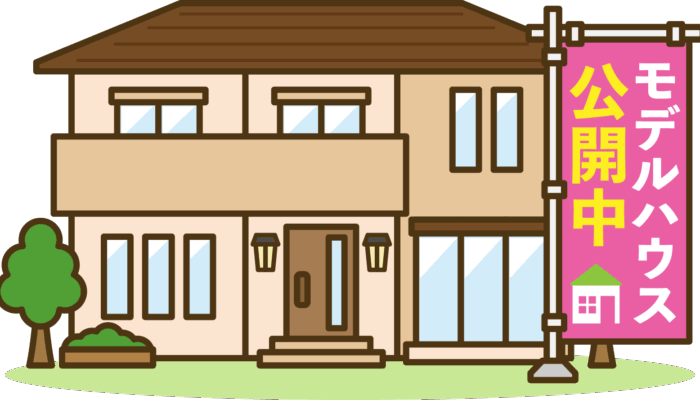
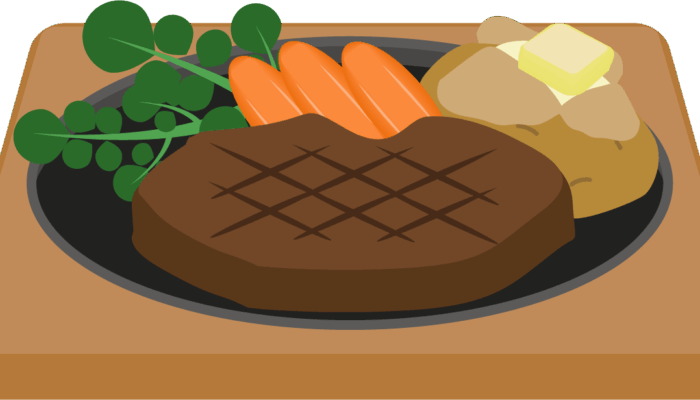
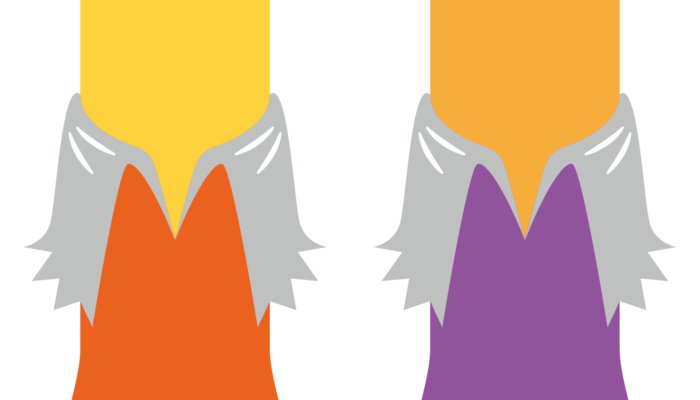




コメント