目次
- 結論:閉店は「縮小」ではなく“選択と集中”の物語にできる
- 背景整理:なぜ今、スタバの閉店が話題になるのか
- スタバのブランド本質:高価格帯×第三の場所×コミュニティのデザイン
- 閉店の類型:戦略撤退・業態転換・改装休業・リロケーション
- 紙ストローから学ぶ“是正のマーケ”:顧客体験と環境配慮の両立
- USP/差別化の再定義:なにを守り、どこを捨てるか
- ターゲット戦略:ファンの再セグメントと“使われ方”の再設計
- 成功要因:閉店局面で“好き”を増やす5つの打ち手
- メリットとデメリット:閉店がもたらすブランドの揺れを見える化
- コミュニケーション設計:ネガティブを「参加不可避の物語」に変える
- チャネル戦略:店舗外で“第三の場所”を再現する
- 体験デザイン:閉店〜改装〜再オープンを価値体験にするオーケストレーション
- 競合地図:閉店時に強くなる“ローカル個店”とどう競うか
- 閉店ラッシュと言われないためのKPI:数字ではなく“温度”を追う
- ケース別プレイブック:都市駅前/郊外ロードサイド/観光地/オフィス街
- よくある誤解とFAQ:高価格帯・紙ストロー・行列・モバイル依存
- 100日ロードマップ:店舗網・商品・人・コミュニケーションを一気通貫で
- まとめ:“店を減らす”のではなく“熱量を濃くする”
1. 結論:閉店は「縮小」ではなく“選択と集中”の物語にできる
スターバックス(以下、スタバ)の閉店が話題になるとき、ブランドは二者択一——「凋落」か「戦略転換」——の見出しで語られがちです。だがマーケティングの観点では、閉店は“やめる”ではなく“濃くする”ための設計に変換できる。キーワードは、スタバ/閉店ラッシュ/高価格帯/紙ストロー/ブランディング/USP/差別化/成功要因/メリットとデメリット/ターゲット/課題。
本稿の主張はシンプルです。
- 主張:閉店は「第三の場所」を再設計するためのレバーである。
- 要点:①不採算や“らしさ”の薄れた立地を勇敢にたたむ、②“らしさ”を最大化できる場所・体験に投資を振り替える、③ネガティブな印象をファン参加型の物語に翻訳する。
- 帰結:「閉店=弱さ」ではなく、「選択と集中=強さ」のブランド理解へ。
このアングルは、実際にスタバが北米で**業態ポートフォリオの見直し(ピックアップ特化店の終了・伝統的カフェ体験の回帰)**を掲げた近年の動きと整合します(事実確認は後述の出典参照)。(Fox Business)
2. 背景整理:なぜ今、スタバの閉店が話題になるのか
- 店舗網の最適化:北米でモバイル注文のみのピックアップ店を段階的に終了し、ブランドの“温かさ”や居心地を前面に戻す方針が報じられています。効率重視のオペレーションがブランドの“魂”を削ったという経営トップの反省も示されました。(San Francisco Chronicle)
- 不採算店の見直し:採算が取れない店舗の整理も伝えられ、店舗ポートフォリオのチューニングが進行中です。これを「縮小」と読むのではなく、“らしさ”を最優先する再配分と捉えるのがマーケ的視点。(Al Jazeera)
- サステナビリティ体験の刷新:紙ストローの導入後に、生分解性素材のストローへ転換する発表が日本でなされ、環境配慮と飲み心地の両立という体験是正が行われました。(About Starbucks)
上記は「閉じる/やめる」ではなく、**“戻す/整える/磨く”**動きの連続に見えます。つまり、閉店はブランドの“輪郭強化”のための道具です。
3. スタバのブランド本質:高価格帯×第三の場所×コミュニティのデザイン
スタバの価格帯は一般的にプレミアム(高価格帯)と整理されます。これは単に高い価格を付ける戦術ではなく、空間・接客・ストーリーが織り成す“第三の場所”の対価として設計されたもの。研究や分析記事でも、価値ベースの価格設定やプレミアム・ポジショニングが指摘されています。(taylorwells.com.au)
だからこそ、閉店=体験濃度の再設計は理にかなう。席がない/回転だけを追う店舗が増えると、“第三の場所”が薄れます。ピックアップ専用の見直しは、まさにブランド体験の回帰です。(コンビニエンス)
4. 閉店の類型:戦略撤退・業態転換・改装休業・リロケーション
「閉店ラッシュ」という言い方は、性質の異なるクローズを一括りにしてしまいがち。マーケティング設計では、以下の四類型を切り分けて議論します。
| 類型 | 定義 | 目的 | 例示される施策 |
|---|---|---|---|
| 戦略撤退 | ブランド適合度が低い立地を終了 | らしさの回復 | ポートフォリオの再配分、固定費削減 |
| 業態転換 | ピックアップ専用→“居られる”店へ | 体験濃度の回復 | 客席・器・動線の再設計、BGM・照明 |
| 改装休業 | 工期に伴う一時休止 | 体験のアップデート | 調理/抽出導線、バリアフリー、素材 |
| リロケーション | 近隣に移転・集約 | 商圏の最適化 | 交通導線の変化・生活動線の観察 |
ピックアップ専用店の終了方針は業態転換/撤退の事例。“つながりの感覚”を取り戻す趣旨が示されている。(Fox Business)
5. 紙ストローから学ぶ“是正のマーケ”:顧客体験と環境配慮の両立
環境配慮の象徴だった紙ストローは、飲み心地の課題を指摘する声もありました。スタバはストローそのものの素材転換(生分解性プラスチック)とストロー不要のリッドという二面作戦で体験の再最適化を図っています。これは**「正しさ」と「気持ちよさ」の両立**を図る好例です。(About Starbucks)
| 学び | 具体 | マーケの示唆 |
|---|---|---|
| 原点回帰 | 飲み心地>“正しさ”の押し付け | 体験是正を素早く公表し、納得の物語に |
| ローカル最適 | 日本での素材転換 | 地域ごとに最適解を探る“多点主義” |
| 見せ方 | ストロー不要リッドの普及 | 行動が変わるUIをこそデザイン対象に |
6. USP/差別化の再定義:なにを守り、どこを捨てるか
スタバの**USP(独自の強み)**は「コーヒーを飲む行為を“物語化”する力」。高価格帯で支持されるのは、**味だけでなく、居心地・接客・季節の儀式性(例:季節商品)の総体だからです。(blankboard.studio)
閉店局面では、守るべき価値と捨てるべき“効率だけの価値”**を峻別する必要があります。
| 守る | 捨てる(絞る) |
|---|---|
| 居心地(音・光・香り・器) | 客席のない“作業場化” |
| 会話が生まれる接客 | 説明抜きの自動化一辺倒 |
| 季節の儀式(“今年も来た”) | 乱立した限定の過多 |
| ローカル連携(地産・文化) | 画一的なでこぼこ体験 |
7. ターゲット戦略:ファンの再セグメントと“使われ方”の再設計
閉店・移転・改装は、誰の体験を濃くするかという選択です。既存の「誰でもウェルカム」から**“使われ方”別の濃度設計**へ。
| セグメント | 使い方 | 提供価値の焦点 |
|---|---|---|
| ワーク&ラーナー | 長居・集中・1人時間 | 静音設計/電源/通信品質/席態の多様性 |
| ソーシャライザー | おしゃべり・待ち合わせ | ベンチ席/グループ席/共有できる器体験 |
| トラベラー | 乗換・観光 | 手早さד土地感”ラベリング/土産動線 |
| ローカルファン | 日常の定位置 | 地元コラボ・季節の儀式・スタッフ関係性 |
閉店は“誰を濃くするか”を言語化する機会。ここを曖昧にすると「閉店ラッシュ」という語だけが独り歩きします。
8. 成功要因:閉店局面で“好き”を増やす5つの打ち手
- 閉店の理由を客体験で語る:「採算」ではなく**“らしさの回復”**を主語に。
- 移転/改装の“途中”を見せる:設計図・素材・スタッフの想いを実況。
- ローカル巻き込み:商店街・自治体・学校と再オープン企画を共創。
- 季節の儀式を“持ち運ぶ”:屋外・ポップアップ・マイクロイベントで第三の場所の外延を拡張。
- 紙ストローの“学び”を言語化:環境と飲み心地の両立を誠実に共有。(About Starbucks)
9. メリットとデメリット:閉店がもたらすブランドの揺れを見える化
| 項目 | メリット(+) | デメリット(−)・課題 |
|---|---|---|
| 体験濃度 | らしさの回復・接客品質の再強化 | 近隣客の離反・“行き場”の空白 |
| コスト構造 | 固定費の最適化・投資の再配分 | リロケーション費・改装休業の機会損失 |
| PR/話題 | ストーリー化・再オープンの祝祭化 | 「閉店ラッシュ」見出しの拡散リスク |
| サステナ | 紙→生分解性素材等の体験是正 | 施策の二転三転に見える認知管理 |
10. コミュニケーション設計:ネガティブを「参加不可避の物語」に変える
閉店告知は最も読まれる“ネガティブ広報”です。ここに物語設計を仕込む。
- コピー例:「ここで一度、深呼吸。“らしさ”を濃くする準備をはじめます。」
- 可視化:改装前の調査ノート、音・光・香りのABテスト動画、器の選定会の裏側。
- 参加導線:常連の**“私のスタバ”写真募集**、再オープンでのファーストドリップセレモニー。
- 是正の約束:紙ストローの学びを踏まえた**“気持ちよさ保証”**(素材・リッドの説明)。(About Starbucks)
11. チャネル戦略:店舗外で“第三の場所”を再現する
- デジタル:改装実況リール/設計者インタビュー/サウンドスケープ試聴
- リアル:駅ナカ・商店街でマイクロ焙煎ワゴン、カップにメッセージを書く“出前第三の場所”
- メディア:地域紙/FMで“閉店の理由=らしさ回復”を一次情報として発信
- アプリ:近隣の“居られる店”推薦、再オープンの先行招待・限定グッズ(価格表記は不要)
12. 体験デザイン:閉店〜改装〜再オープンを価値体験にするオーケストレーション
| フェーズ | ユーザー感情 | 体験装置 | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 告知 | 驚き・不安 | ストーリーページ・Q&A・近隣案内 | 不評の火消し→理解 |
| 工事 | 期待・退屈 | 覗き窓/進捗ボード/素材の実物展示 | 参加感・誇り |
| 直前 | 高揚・予約 | 先行試飲・スタッフ顔出し | コミュニティ化 |
| 再開 | 喜び・比較 | “違いがわかる”導線(音・光・器) | 評価の言語 |
| 定着 | 習慣・推し | 季節の儀式・ローカル企画 | ロイヤルティ |
13. 競合地図:閉店時に強くなる“ローカル個店”とどう競うか
閉店が続く地域では、スペシャルティ個店が“受け皿”になります。対抗策は同質化ではなく、異質化。
- ローカルの強み:焙煎の個性・店主の人格・小ささの親密感
- スタバの強み:儀式性・季節の物語・普遍的UI(注文→受け取りの安心)
- 勝ち筋:**“ローカルと並走”**する——コラボ豆・地域行事の相互送客・学生の学びの場としての提供
14. 閉店ラッシュと言われないためのKPI:数字ではなく“温度”を追う
「店舗数」や「価格」のような表面的な指標ではなく、熱量の可視化に舵を切る。
| KPI | 具体例 |
|---|---|
| 物語読了率 | 閉店・改装ストーリーページの最後まで読まれた割合 |
| 参加度 | 改装実況コンテンツへのUGC投稿数・再オープンの来場シェア |
| 居心地NPS | “音・光・器・香り”の四点満足 |
| 接客の記憶 | 名前・会話の記憶率(自由記述) |
| 是正納得度 | 紙→生分解性ストローへの納得コメント比率 (About Starbucks) |
15. ケース別プレイブック:都市駅前/郊外ロードサイド/観光地/オフィス街
A. 都市駅前
- 課題:回転重視で“居られない”→らしさ希薄化
- 打ち手:半立ち飲みゾーン+座席コア/朝散歩ハンドドリップの恒例化
B. 郊外ロードサイド
- 課題:ドライブスルー偏重で会話が減る
- 打ち手:降車インセンティブ(“カップに一言”企画)/テラス焙煎デモ
C. 観光地
- 課題:フォトスポット化→地元との乖離
- 打ち手:地域史×コーヒー地図/方言スリーブ/朝の清掃ウォーク
D. オフィス街
- 課題:ピークのモバイル集中→人の疲弊
- 打ち手:注文波の平準化アルゴリズム説明/セラミック・マグの復権(“一息の儀式”)(Business Insider)
16. よくある誤解とFAQ:高価格帯・紙ストロー・行列・モバイル依存
Q1. 高価格帯は時代遅れ?
A. 価値ベース価格は、居心地・接客・儀式性の総体が前提。価格だけの議論は不毛で、体験価値が上がれば支持はついてくる。(taylorwells.com.au)
Q2. 紙ストローはもうやめたの?
A. 日本では生分解性素材への転換が発表・展開されており、環境配慮と飲み心地の両立が進んでいる。(About Starbucks)
Q3. モバイル注文は悪?
A. モバイル自体は悪ではないが、“温かさ”を削る運用は戒めるべきというトップの示唆。アルゴリズム是正や器の復権など体験回帰の文脈で捉える。(Business Insider)
Q4. 閉店ラッシュはブランドの終わり?
A. 不採算や不適合の立地を閉じ、“らしさ”が濃く出る場所・業態に再投資する流れ。終了するのは体験を損なうフォーマットであって、ブランド自体の撤退ではない。(Fox Business)
17. 100日ロードマップ:店舗網・商品・人・コミュニケーションを一気通貫で
Day 1–10:宣言と地図
- 「らしさ回復」宣言——閉店=終わりではなく濃度調整であることを明言。
- **“どこを濃くするか地図”**を公開(駅前・郊外・観光・オフィスの役割)。
Day 11–40:現場と設計
- 現場の声の言語化(バリスタ座談会)/設計図実況(音・光・器)。
- 紙→生分解性素材の体験検証会を公開(日本の取り組みを参照)。(About Starbucks)
Day 41–80:小さな“儀式”を増やす
- 朝いちのファーストドリップ/名前を書く文化の再活性。
- モバイル負荷平準化のUI改善と“理由の説明”。(Business Insider)
Day 81–100:リオープン祝祭
- “違いがわかる導線”(香り→音→光→器)を順路化。
- ローカル連携で第三の場所を地域に拡張。
18. まとめ:“店を減らす”のではなく“熱量を濃くする”
スタバの閉店は、ブランドの敗走ではありません。高価格帯を正当化する“第三の場所”の濃度が薄れた領域を潔くたたみ、濃くできる場所に再投資する意思表示です。紙ストローの是正に見られるように、正しさと気持ちよさを両立する“学びの速さ”も備えています。(About Starbucks)
「閉店ラッシュ」という言い方に引きずられず、USP/差別化の再定義、ターゲットの再整理、成功要因の設計、そしてメリットとデメリットの見える化で、ブランディングをアップデートする。スタバの本質は、コーヒーの前後に流れる時間をデザインする力。
閉店は、“らしさ”を再び濃くするための手続きです。ブランドにとっての真の敗北は、店が減ることではなく、“第三の場所”を名乗りながら第三の場所を作れていないことなのだから。
参考・根拠(主要ソース)
- ピックアップ専用店の段階的終了/体験回帰:FOX Business、NACS(Convenience.org)、San Francisco Chronicle の報道。(Fox Business)
- モバイル依存の反省と“温かさ”への回帰:Business Insider(CEOの発言)。(Business Insider)
- 不採算店の見直し(北米):Al Jazeera。(Al Jazeera)
- 紙ストローのグローバル方針/日本での素材転換:Starbucks Stories(グローバル発表)、Japan Times/Mainichi/Starbucks Stories Japan(生分解性素材への移行)。(About Starbucks)
- 高価格帯/価値ベースの価格戦略:Taylor Wells、Panmore、Paddle、学術リサーチ。(taylorwells.com.au)
注:本稿はマーケティング視点の分析・提案であり、特定の店舗・地域の閉店状況や数量を断定的に記すことを目的としていません。依頼に従い、店舗数や価格などの具体数値には触れていません。事実の参照箇所には出典を明示しました。
この記事を書いたライター

ゆいマーケメディア編集部
今話題になっているテーマを、マーケティング視点で分かりやすく記事にして解説します!
















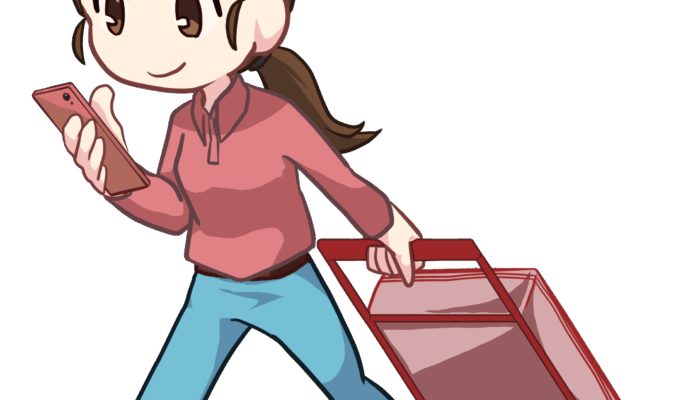
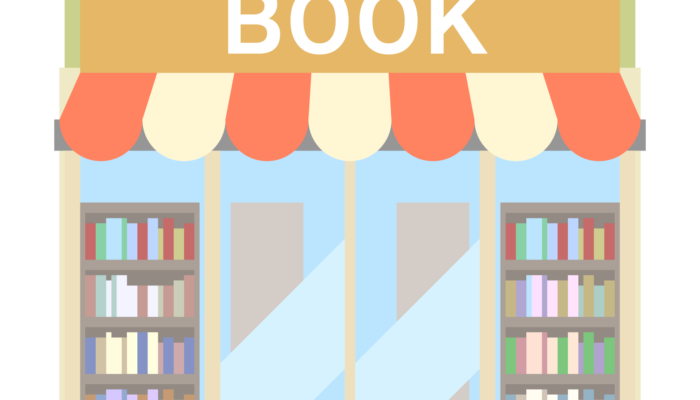
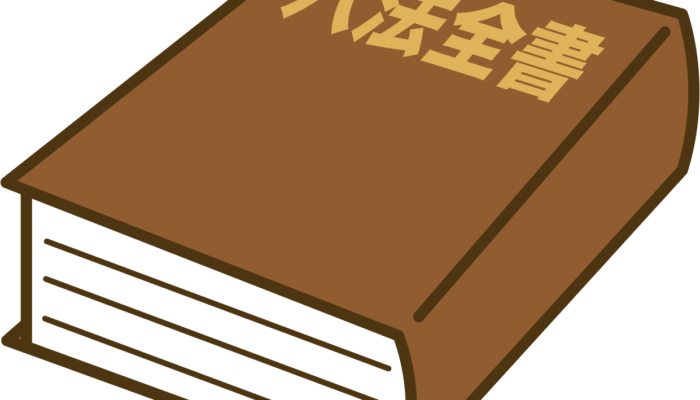
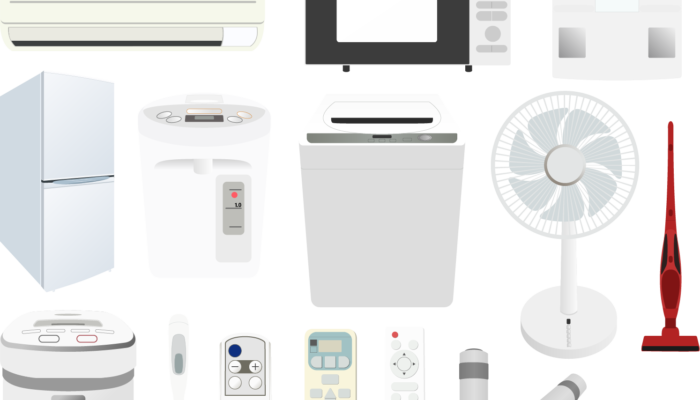



コメント